フルートはそのキラキラした外見から、金管楽器と思われがちですが、実は木管楽器に分類される楽器です。
本記事では、フルートが木管楽器とされる理由を「エアリード」という音の仕組みや歴史的背景からわかりやすく解説します。
また、なぜ金属製のフルートが普及したのかについても詳しくご紹介します。
これを読めば、フルートの魅力や分類の秘密を深く理解できるでしょう。
- フルートが木管楽器と分類される理由
- エアリードの仕組みと音の発生原理
- 木製から金属製に変化したフルートの歴史
- 金管楽器との違いと分類基準
フルートはなぜ木管楽器と呼ばれるのか

木管楽器の定義とは
木管楽器とは、音を出す仕組みに基づいて分類される楽器です。その名前から「木で作られた楽器」と思われがちですが、材質は問われません。重要なのは、空気やリードを振動させることで音を出す点です。
具体的には、木管楽器には以下の特徴があります。
- 管に穴があり、その穴を開閉することで音の高さを調整する。
- リードを振動させるか、空気を直接振動させて音を発生させる。
- 音の発生源が演奏者の唇の振動ではない。
例えば、クラリネットやサックスはリードを使用して音を出し、フルートやリコーダーは空気を振動させる「エアリード」の仕組みで音を出します。このため、材質が金属であってもフルートは木管楽器に分類されます。木管楽器の定義は、材質ではなく発音原理で決まるのです。
金管楽器との違いについて
金管楽器との最大の違いは、音を出す仕組みにあります。金管楽器は、演奏者が唇を振動させることで音を発生させる「リップリード」の原理を利用しています。一方、木管楽器はリードや空気の振動を使用します。
具体例を挙げると、トランペットやホルンなどの金管楽器は、マウスピースに唇を当て、その振動を管内に伝えることで音を出します。このため、金属以外の材質であっても「リップリード」で音を出す楽器は金管楽器に分類されます。
このように、木管楽器と金管楽器の違いは、音を出すための物理的な仕組みによって明確に区別されます。そのため、フルートが金属製であっても、エアリードの原理によって木管楽器とされるのです。
昔は木で出来ていたフルート
フルートは、現在では金属製の楽器として広く知られていますが、かつては木で作られていました。特に17世紀から18世紀にかけてのバロック音楽の時代、フルートは「フラウト・トラヴェルソ」と呼ばれる木製の横笛でした。
その材質としては、グラナディラやボックスウッドなどの木材が一般的に使用されていました。
木製のフルートは、温かみのある柔らかな音色が特徴でしたが、以下の理由で金属製に移行しました。
- 木製では、湿度や気温の変化に弱く、音程が不安定になりやすかった。
- 音量が小さく、広い会場では他の楽器に負けることが多かった。
- 製造における精密さや耐久性が金属の方が優れていた。
19世紀、フルートの製造技術を大きく革新したテオバルト・ベームが金属製フルートを開発しました。
この新しいフルートは、安定した音程と大きな音量を可能にし、現代のフルートの原型となりました。木製の時代からの進化は、楽器としての性能を飛躍的に向上させたといえます。
エアリードとリードの違い
フルートが音を出す仕組みである「エアリード」と、クラリネットやサックスなどで使用される「リード」の違いは、音の発生に関わる振動の仕組みにあります。
エアリードの特徴
- エアリードとは、空気そのものを振動させて音を発生させる方法です。
- フルートでは、唄口のエッジ部分に息を吹き込むと、空気がエッジに当たって振動し、音が生じます。
- 例えるならば、瓶の口に息を吹きかけて音を出す「ビン笛」と同じ仕組みです。
リードの特徴
- リードは薄い板状の素材(通常は植物の葦)を振動させて音を発生させます。
- シングルリードの場合(例:クラリネット、サックス)、1枚のリードを振動させます。
- ダブルリードの場合(例:オーボエ、ファゴット)、2枚のリードを使って音を出します。
- リードは消耗品であり、音色を変えたい場合にはリードを交換することも可能です。
この違いにより、エアリードは繊細な息のコントロールが求められる一方で、リードは音の強弱や質感に独特の味を加えることができます。それぞれの仕組みが楽器の個性を大きく形作っているのです。
フルートが金属製でも木管楽器な理由
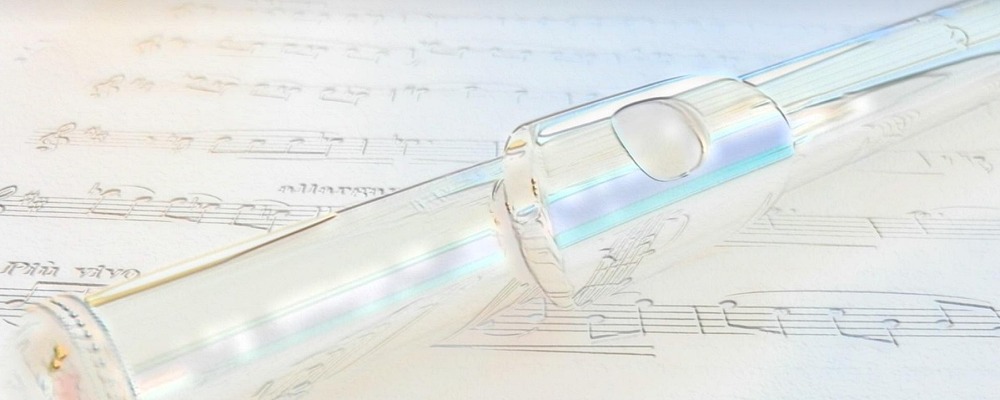
フルートの発音原理を解説
フルートが木管楽器に分類される大きな理由は、その発音原理にあります。フルートは「エアリード」という仕組みで音を出します。
演奏者が唄口に息を吹き込むと、その息がエッジ部分に当たり、内部と外部の空気が振動を起こします。この振動が音を発生させる仕組みです。
他の木管楽器、例えばクラリネットやサックスはリードを使いますが、フルートは空気そのものを振動させるのが特徴です。
この仕組みは、ビン笛のようなイメージで、息をどの位置に、どの強さで吹き込むかが音の生成に影響します。
現代のフルートの素材について
現代のフルートは主に金属で作られており、代表的な素材には銀、洋銀(ニッケルシルバー)、プラチナなどがあります。これらの金属が選ばれる理由は、以下の通りです。
- 耐久性と安定性
木材に比べて金属は湿度や温度の影響を受けにくく、安定した音程を保つことができます。 - 音量と音色の向上
金属製のフルートは音量が大きく、遠くまで音を届けることが可能です。また、明るく澄んだ音色を生み出すことができるため、オーケストラや吹奏楽など多くの場面で重宝されています。 - 製造の精密さ
金属は加工がしやすく、フルート特有の複雑なキー構造を正確に作ることが可能です。これにより、演奏者がスムーズに演奏できるようになっています。
歴史的には木製のフルートが主流でしたが、金属製のフルートはこれらの特性により、より幅広い演奏スタイルに対応可能となりました。
まとめ:フルートが木管楽器である理由
フルートが木管楽器である理由は、発音原理に基づいています。金管楽器は演奏者の唇を振動させる「リップリード」の仕組みを持つ一方で、木管楽器は空気やリードを振動させる仕組みを持っています。
フルートはエアリードを利用しており、金属製であるにもかかわらず、音を出す方法が木管楽器の分類基準に合致しているのです。
また、金属製であることによる利便性や性能の向上が、現代フルートの普及を支えています。しかしその根底には、木管楽器としての本質的な特性が息づいており、これがフルートを木管楽器たらしめている理由です。
この分類基準を知ることで、フルートの魅力や歴史的な背景をより深く理解できるでしょう。
記事のポイントをまとめます。
- 木管楽器は音を出す仕組みに基づいて分類される
- 木管楽器は材質ではなく発音原理で決まる
- 管に穴があり、開閉によって音の高さを調整する
- 空気やリードを振動させて音を出すのが特徴
- 演奏者の唇の振動を使わない楽器が木管楽器
- フルートはエアリードの仕組みで音を発生させる
- エアリードは空気を直接振動させる方法である
- 金管楽器は唇を振動させるリップリードを利用する
- フルートは金属製でも音の仕組みが木管楽器に該当する
- 歴史的にフルートは木で作られていた
- 木製フルートは柔らかな音色を持つが気候に弱い
- 金属製フルートは安定した音程と音量を実現する
- 金属製フルートの素材は銀やプラチナが多い
- フルートは製造技術の進化で性能が大幅に向上した
- 木管楽器と金管楽器は音の発生方法で明確に区別される


